
¢RÌ©RwZ2007
æ13ñu~Ì¢REC¹®v
y2011/9/21 XVz

¢RÌ©RwZ2007
æ13ñu~Ì¢REC¹®v
y2011/9/21 XVz
|
ú@216ú(y) 10:00`15:30
ê@¶cÎn QÁÒ@PÇ@xº½A_RKëAªèNîARàá @@@@QÇ@_Rà¢A¡}LÆA{kCA¬qD¢AìñÀA]Ë[ @@@@RÇ@éØuàAöèîaAúì´ÀqAXYå @@@@SÇ@à¡éAÃc A{½gV @@@@TÇ@RàtAÅ´ÑóA{cåMAÚì}¢Ã@@21l@ ut@âcb¶AâcFüA¡ÔûXqAbª¾YAR{W ¢RÌ©RwZ2007ÌÅIúAæ13ñu~Ì¢RvðJõܵ½BßOÍ~Ì¢Rðà«AßãÍC¹®ðsȢܵ½B 12Ì¢RÌ©RwZ©çÍ©É2ªoßµ½¾¯ÈÌÉAqÇཿ̬·AÏ»ÉÍÁ©³êܵ½B 

ÂNÈwÙðo·éÉ©ªÌÌÅC·ðªµÄàç¢Üµ½B C·Í6ŵ½ªAÌÅC·ð´¶Æé±ÆÍ\ïµ¢æ¤ÅAOã5`6xÌÍÍŪUµÜµ½B ·à¯lÅAÈ©È©½èܹñB¬ rÌ ·Í6ŵ½B 

PLÌ÷çºÉBêĢ鶨ðTµÜµ½BN⽩¯èÅ«È¢¶¨ªBêĢܵ½B 











µ»ÉoÁÄAkö±Ìe©çJËÖ~èܵ½B GèXVnæÅ~ÌGØÑÌtÌ´Gð¡í¢Üµ½BtªúÍϵĢܷB 













¿½ØÉAå«ÈTmRVJPð©Â¯Üµ½B nmLÑÅA½Ìæ[ð©ã°ÄAnmLÌYÔÆÔð©Â¯Üµ½BnmLÑÌÛS®É¢ÄàAµ×µÜµ½B ±ê¾¯ÌÌnmLªWÜÁĶ¦Ä¢énmLÑÍ_Þ짺Å࿵¢Ì¾ÆྵÄàA檩çÈ©Á½©àmêܹñB ñAnmLÑðÊÁÄ¢éÆÍ¢ÁÄàAqÇཿÌÖSÍrÌAJUKjÉ Á½©çÅ·B 

¼nĶnÌÓÉÍt\fiMªçÌWp[ðE¢ÅAZ[^[É Ö¦Â éƱëŵ½B¶cÎnÅÍBêÌiMÅ·B»ÌèðÏ@µÜµ½B 
cÞÉܵ½BÄɧĽÄRqðÐïé±Æɵܵ½B 



ãÌcÞÌú½èÌ«¢Æ±ëÉÍXª£ÁĢܵ½Bú¢Æ±ëÅÍ2cmÉàBµÄ¢ÄAqÇཿͲÉÈÁĵܢܵ½B 











TiMÌEkð©Â¯Üµ½B 



cÞüÓÌnÉÍIICkmtOªç«¾µÄ¢Üµ½B 





AY}qLKGÌYÍܾnÜÁĢܹñB 
ËBs®¸ÕÅLOÊ^ðBèܵ½B 









e`RLêÌVïðVµ·éHªnÜÁĢܵ½B 
µ»Ì÷ÌÉRdiTVKÌWcz~ðÏ@µÜµ½B 






ÂNÈwÙÉßÁÄ©ç¨Ì¨Ùɵܵ½B ßãÍA1NÔÌv¢oð´z¶âGÉ\»µÄàç¢Üµ½B 
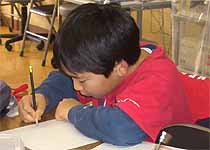













C¹Øö^®ðsȢܵ½B¡NxÌFÎÜÍSlŵ½B 





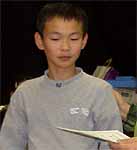








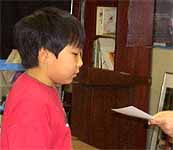


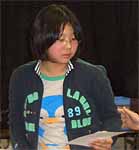


GØÑÌXV̽ßÌcÃè̽ßhOE¢ÆA¦ÝÉQÁµÄê½qÇà4l(2lÍÈ)AÌrÌO¶¨ììíÉQÁµÄê½qÇà2lÉA crIg[vÇ©çÌ´Óóðö^µÜµ½B ¶cÎnÌ©RðÛS·é½ßÌ{eBA®ÉQÁµÄê½±Æð]¿µ½¢Æv¢Üµ½B 

©W{ÃèÉQÁµÄA®¬µ½W{ðó¯æÁĢȩÁ½qÇàÉìiðnµÜµ½B 

FÅÅ«é©R²¸(Z~²¸)ÉQÁµÄê½qÇཿÉÍA¡NxÌZ~²¸ñðnµÜµ½B 
¡NxÌ¢RÌ©RwZÍAÁÊñà½AßÄÌnaïð23úÅJ÷éÈÇÌVµ¢Ýà èAC¹®ÜÅð³ÉI¦ÄzbƵĢéƱëÅ·B ¯ÉAQÁÒêlêlÉ¢ÄÌlXÈoªv¢N±³êAyµ·©¢]Cð´¶Ä¢Ü·B ÆÍA1NÔÌ®ÌÜÆßðÂÁÄQÁÒÉéìÆA¬àÉÖ·éïvÌÜÆßðsÈÁÄñðño·é±ÆÈÇðc·ÌÝÅ·B ùÉANxÌ¢RÌ©RwZÌQÁÒåWànßĨèAPV¼ÌQÁ\ð¾Ä¢Ü·ªAVlÌ\Í¢¾5lÉܹ߬ñB Æ5lÁ¦ÄA10lÌVlÍ~µ¢ÆvÁĢܷªAÁÊÈoqàµÄ¢È¢±Æðl¦éƪǷ¬éÌ©àmêܹñB 2NÚA3NÚANxÍSNÚÆ¢¤QÁÒÉεÄAÇÌlȳçðl¦ê΢¢Ì©A ÊívOÍß½àÌÌnaïÍǤµ½àÌ©A ÆAܽNxÆÉ¢ÄÌYݪnÜÁĢܷ |
 ©í³«©R²¸cÌ®Ìy[W
©í³«©R²¸cÌ®Ìy[W